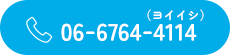- 手・足・顔のむくみは何科を
受診すべき? - むくみ(浮腫)について
- 塩分・水分・血流が関係?むくみの原因
- 朝と夜で違う?むくみの症状チェック
- 放置すると危険?むくみの受診目安
- 手・足・顔…部位別むくみの原因と
考えられる病気 - むくみセルフケア・対策・予防法
手・足・顔のむくみは
何科を受診すべき?
むくみは健康状態に問題がなくても起こりうることですが、中には数日から数週間続くものもあり、その裏に疾患が関わっていることがあります。
 以下のような心当たりのある方は、循環器内科への受診をご検討ください。
以下のような心当たりのある方は、循環器内科への受診をご検討ください。
- むくみが1日で治まらない
- むくみ以外にも症状がある
- ふくらはぎの血管がデコボコと浮き出ている
- 発熱や痛みを伴うむくみがある
など
大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科では、循環器疾患の診療も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
むくみ(浮腫)について
「むくみ」とは、何らかの原因によって体内の水分バランスが変動し、皮膚や皮膚の下に水分がたまっている状態を指し、通常は疾患扱いになりません。
医学的には浮腫(ふしゅ)と呼ばれ、重力や姿勢の影響によって少なからず「むくむ」ものです。例えば夕方に靴下の跡がついている程度であれば正常の範囲内です。
塩分・水分・血流が関係?
むくみの原因
むくみの主な原因は、毛細血管から血管外(細胞)へ水分が溜まること、毛細血管やリンパ管への水分吸収量が減少することが挙げられます。
血管内外や細胞の水分量を一定に保つためには、心臓や腎臓の機能・血管内の塩分濃度・血管の流れなどが整っている必要がありますが、いずれかの機能が障害された場合にむくみが生じるのです。
高齢者に多い足のむくみの原因
ご高齢の患者さんに見受けられるむくみは、主に身体機能や臓器の働きの加齢による衰え、長時間同じ姿勢で過ごすことが原因と考えられています。
食事量が低下して栄養不良になると低アルブミン血症となり血管内の水分が血管外に漏れて全身に浮腫みが生じることも多いです。
血管が硬くなる
加齢とともに血管の硬化が進むと、血管の柔軟性が落ちるため血流が滞りやすくなります。特に足の血管は細く、心臓から遠いため血液がたまりやすい構造です。このような理由により足のむくみが現れます。
心機能が低下する
心機能の衰えにより血液を送り出すポンプ機能も徐々に低下します。この機能低下により下肢全体の血流も悪くなるため、足のむくみが発生しやすくなります。
筋力が低下する
足の筋肉は、血液やリンパ液の循環促進作用を担っており、体の上部へと押し上げる役割を果たしています。
しかし筋力が落ちると循環を促すことも難しくなり、足がむくみます。
朝と夜で違う?
むくみの症状チェック
むくみは、主に夕方から夜にかけて現れやすいです。
普段から朝と夜に2回セルフチェックを行うことで比較と観察ができて、異常の早期発見につながります。
以下のチェックポイントを参考に、ご自身でチェックしてみてください。
むくみ症状チェックポイント
チェックポイントは3つあります。
①靴下のゴム跡
 夕方になると朝から履いている靴下の跡が残ることがあります。
夕方になると朝から履いている靴下の跡が残ることがあります。
跡の深さや、靴下を脱いでから跡が消えるまでにかかる時間を観察しましょう。
②足のすね
足のすねを親指などでグッと5秒押してみてください。
指を離した時のへこみが10秒以上経っても戻らない場合は注意が必要です。
③朝と夜の足の太さ
日々重力の影響で足に水分が溜まりやすくなるため、夕方はむくみが強く足が太くなったように感じられます。
特にデスクワークなどで長時間同じ姿勢でいることが多い人は、足のむくみや静脈瘤があるか観察を続けましょう。
上記のチェックポイントに複数当てはまる場合やむくみが気になる場合は、当院へご相談ください。
放置すると危険?
むくみの受診目安
一晩寝ただけで解消される軽度のむくみは、基本的に心配いりません。
しかし以下のような症状が見られたら、救急車の要請や診察が必要です。
すぐに救急車を呼ぶべき症状
- 食後に顔がむくみはじめた
- 医薬品の内服後に急に体がむくむ
- 蕁麻疹や呼吸困難感を感じる
など
早急な受診が必要な症状
- 数日間かけて少しずつ顔や足がむくむ
- 新しい医薬品を内服後にむくみが現れた
- むくんだ皮膚を押すと指の形が残る
など
なるべく近日の受診が必要な
症状
- 夜間息苦しく横になれない
- 発熱後1週間以内にむくみが生じた
- 尿が泡立つようになった
など
1ヶ月以内に受診すべき症状
- 関節痛を伴う
- 下肢静脈瘤がある
- 肝機能障害及びむくみがある
など
注意すべき他の症状
- 体重の急激な増減
- 脈拍が異常に速いまたは遅い
- 強い疲労感がある
など
むくみの原因疾患には、溶連菌感染後糸球体腎炎などの重篤なものもあります。
特にむくみ以外の体調変化を伴う場合は、すぐに当院へご連絡ください。
手・足・顔…部位別むくみの
原因と考えられる病気
手のむくみの原因・病気
リンパ浮腫
主にリンパ系疾患に罹った場合や乳がんのリンパ郭清を行った後に、リンパ液の排出が滞るため手にむくみが生じます。
腎臓疾患
腎臓機能が低下する場合に、尿生成の減少や老廃物の滞留が生じるため体内の水分が過剰に溜まり、溜まった体液によって手にむくみが現れることがあります。
長時間同じ姿勢
長時間手を使う作業や姿勢が悪い状況が続く場合、脇の下などの血液やリンパ液の流れが悪くなり、手がむくむことがあります。
足のむくみの原因・病気
下肢静脈瘤
下肢静脈瘤は、静脈弁の機能不全によって形成される「静脈のコブ」です。本来は、足の静脈血管内にある静脈弁によって血液の流れが一方向へ保たれていますが、静脈弁の機能不全が起きると、次第に血液が滞留し、足のむくみを伴いながら静脈が膨れていきます。
これにより足の皮膚表面に「コブが連なる」状態が見受けられるようになるのです。
肺高血圧症
肺高血圧症によって心臓に負担がかかり右心室の働きが悪くなると、静脈圧が上昇して心臓に戻ってくる血液が戻りづらくなり、足がむくみやすくなります。
深部静脈血栓症
(エコノミー症候群)
長時間同じ姿勢で足を動かさない状態でいると、下肢の血流が滞り血栓が生じやすくなります。この血栓は下肢の血流を妨げるため、むくみを引き起こします。
腎臓疾患
腎機能が低下すると、尿生成や老廃物排出が滞ります。この影響を受け、特に下肢の末梢血管は細く体液が貯留しやすく、むくむのです。
妊娠
妊娠中はホルモンの影響で体液を溜めこみやすくなるほか、子宮や胎児の増大によって骨盤内の血管が圧迫されることも関連し、足がむくむことがあります。
長時間の立ち仕事や座り仕事
主に下半身の動きが少なくなる状況が1時間以上続く場合は、股関節の血液やリンパ液の流れが悪くなり、足がむくみやすくなります。
顔のむくみの原因・病気
心不全
心不全になると心臓から十分に血液を送り出せなくなるため、体内に水分が溜まりやすくなります。
すると心臓に滞った血液内の水分が血管外へ押し出されるため、顔がむくむことがあります。
アレルギー反応
食品・医薬品・環境由来のアレルゲンに対するアレルギー反応によって、一時的に顔や唇などが腫れることがあります。
副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔の炎症や感染症によって鼻周囲に膿や免疫物質、体液が溜まるため、顔のむくみを引き起こします。
甲状腺機能低下症(橋本病)
橋本病を発症すると、水分を溜める働きを持つ「ムコ多糖類」が代謝されづらくなるため、水分が全身に溜まりやすくなります。結果として顔がむくむことがあります。
腎臓疾患
腎機能が低下すると、尿生成や老廃物排出が滞り、体内に体液を溜めこむ傾向があります。これにより顔のむくみが現れやすくなります。
全身のむくみの原因・病気
心筋症
通常であれば心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしていますが、心筋症はポンプ機能が低下する疾患です。次第に血液の流れが滞り、体内の水分が血管の外に漏れ出てしまうため、むくみが生じます。
肺高血圧症
肺高血圧症によって心臓に負担がかかり右心室の働きが悪くなると、静脈圧が上昇して心臓に戻ってくる血液が戻りづらくなり、手足・肝臓などがむくみます。
腎不全
腎不全は、血液中の老廃物や水分などをろ過する機能が徐々に低下する疾患です。次第に尿が作られなくなり、溜まった水分などが血管外へと押し出され、足や肺など細胞の間に溜まっていくため、むくみや息苦しさを感じるようになります。
肝硬変
肝硬変になると、本来は肝臓で作られるアルブミンというタンパク質が不足します。
アルブミンは水分を引っ張る働きを持っていますが、不足した場合は血中の水分が血管の外に漏れ出やすくなり、腹水やむくみを引き起こすのです。
甲状腺疾患
甲状腺疾患を発症すると低タンパク血症(低アルブミン血症)になりやすく、血管外へ水分が漏れ出てしまうため、むくみが生じます。
むくみセルフケア・対策・予防法
むくみは、日頃の少しの工夫で軽減や改善することが可能です。
以下のような方法のうち、取り組めるものを日頃の習慣にしましょう。
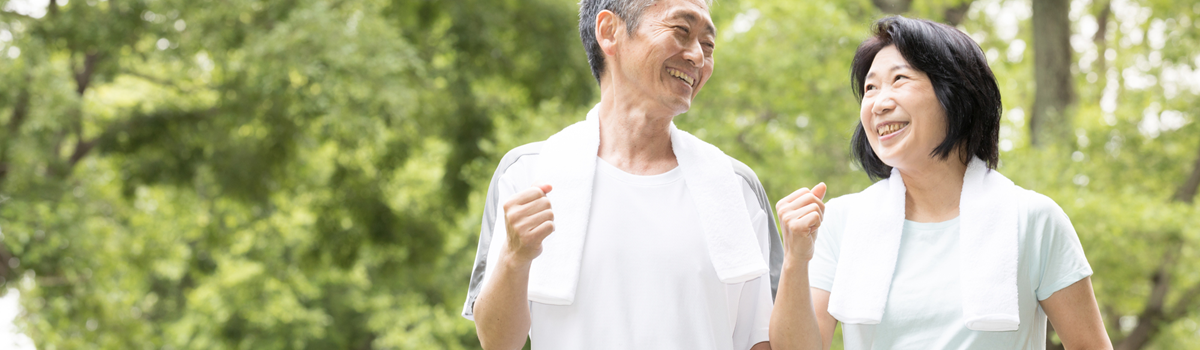
適度な運動
むくみは、血液の巡りを良くしておくと改善されやすくなります。例えば散歩・ラジオ体操・階段昇降・踵の上げ下ろしは、適度な運動として続けやすいでしょう。
塩分摂取を控える
塩分を控えることで、体が水分を溜めこむ状態を避けることができます。もし外食が続くと塩分の過剰摂取につながり、体が体内の塩分濃度を一定に保とうと水分を溜めこむことになります。
なるべく素材の味を楽しめるような減塩調味料を使用し、味の付け方を工夫しましょう。
塩分排出を促す栄養素を摂る
塩分排出を促す栄養素を摂ることが、むくみ予防に効果的です。
例えばスイカ・きゅうり・冬瓜・あずき・バナナ・柿などの果物は利尿作用があり、塩分の排泄を助けるカリウムを多く含みます。
飲酒は適量に
お酒の量とおつまみには要注意です。お酒は、喉を乾かせ水分を摂りたくなる働きをします。これに加えて、おつまみは塩分の濃い味付けになっているため喉が渇き、過剰な水分摂取になりかねません。
弾性ストッキングを着用する
足がむくみやすい方は、弾性ストッキングを着用してみましょう。ふくらはぎや足首を圧迫することで血管やリンパ管を刺激して、足に溜まる血液やリンパ液を血管内へ戻しやすくします。
体を締めつけない服装にする
衣服を選ぶ時は、関節や体を動かしやすく重みの感じにくい服がポイントです。
身体を温める
特に足首や足全体はむくみやすいため、レッグウォーマーや膝掛けを使用したり、足湯をしたりして常に足元を冷やさないように意識しましょう。